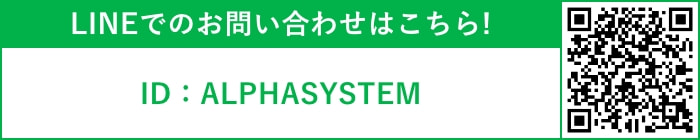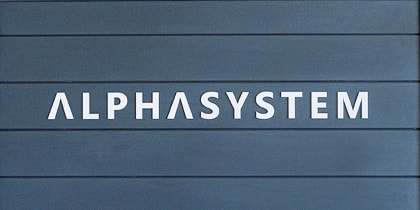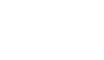設備保全ってなあに?その目的について詳しく知ろう!

オフィスビルなどのメンテナンス管理者の業務は多岐にわたり、ひとりで様々な業務を兼任しているケースも珍しくありません。そのため、設備の不備や故障などの実際に起きている問題に時間を取られ、保全活動は後回しになってしまうケースも多いのではないでしょうか。しかし、設備保全を後回しにすれば、ビル内で働く人に大きな影響が及ぶ可能性や、設備の交換が必要になれば、結果的に大きな手間やコストが発生する恐れもあります。そこで今回のコラムでは、ビル設備の中でも特に、業務用エアコンの設備保全について、その種類や概要、必要性や目的など、幅広くスポットライトを当ててご説明させていただきます。是非一度、目を通してみてくださいね。
設備保全って?
設備保全とは、ビル内にある様々な設備を不備や故障なく維持していくために行う計画的な点検を指します。業務用エアコンでいえば、一般的な耐用年数は13年前後と言われていますが、その間に故障なく最大限の機能を発揮出来るようにするための点検業務が設備保全というわけです。なお、後ほどの項目にて詳しく解説致しますが、設備保全業務には大きく分けて「予防保全」「事後保全」「予知保全」の3種類があり、設備の修理・点検をするという点は共通していますが、それぞれその特徴や違いが異なってきます。
「保守」「修理」「メンテナンス」との違いは?
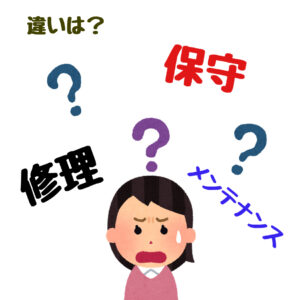
保全に近い言葉に、「保守」「修理」「メンテナンス」などがあります。似たような響きなので一見同じものかと思われがちですが、それぞれ意味合いが異なり、まず保全は、先程もご説明させて頂いた通り、主に機器や設備が不備や故障なく長期間安全に使える状態にするために計画的に行う点検のことを指しています。次に保守とメンテナンスは、故障予知も含め機器の異常・故障を早期発見し、迅速な対応をするための点検を指します。そして最後。修理は、実際に発見された機器や設備の故障を修復することを指しています。つまり、保全が故障前の改善や予防を目的に行うものであるのに対し、保守とメンテナンスは故障予知もしつつ故障後の迅速な対応を主な目的としているということが決定的な違いと言えるでしょう。
設備保全はなんで重要なの?見落としがちになってしまうのはどうして?

ビルメンテナンスの主な業務には「清掃管理」「設備管理」「衛生管理」「保安管理」「管理サービス」などが挙げられます。ビルによっては各業務の担当者がいるケースもありますが、少人数で全ての業務をこなさなければならないビルも存在します。少し前のデータにはなってしまいますが、公益社団法人全国ビルメンテナンス協会が公開している「ビルメンテナンス情報年鑑2022」によると、ビルメンテナンス業を手がける企業において、常動従業員不足は課題のひとつとされており、実態調査の結果を見ても、地区本部別の全体で64.8%が「やや不足」または「不足」と回答しています。更に月商規模別で見てみると、1,000万円未満の企業が56.2%と最も低く、続き1,000万円以上3,000万円未満の企業が62.3%、1億円以上の企業が68.5%、最も高いのが3,000万円以上1億円未満の企業の71.1%となっており、月商規模が大きい方が人材不足の傾向にあることが分かります。メンテナンス業務で人材不足が慢性化してしまうと、どうしても不備や故障が起きた後の対応が中心となってしまい、設備保全業務が後回しになりがちに。しかし、故障やトラブルが起きる前に設備保全を徹底することが出来れば、故障を未然に防ぐことができ、管理者にかかる負担も最小限に抑えることが出来ます。少ない人数でも負担を軽減しつつ、ビル内の快適な環境を維持するために、設備保全は非常に重要な業務と言えるでしょう。
設備保全の種類について
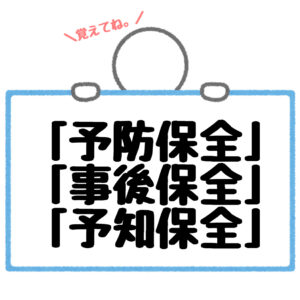
上の項目でも軽く触れさせていただきましたが、設備保全には大きく分けて「予防保全」「事後保全」「予知保全」の3つの種類があります。それぞれの違いや特徴について、ここでは詳しくご紹介させていただきます。大事なポイントでもあるので、しっかりと確認しておきましょう。
予防保全
予防保全は、定期的な清掃・点検により、機器や設備の劣化・故障を予防するために行われます。具体的には、機器や設備ごとに設定されている耐用時間や耐用年数をもとに点検を行います。耐用時間や耐用年数を過ぎたら、故障していなくても交換することで劣化や故障を防止出来るケースも少なくありません。予防保全は、後に記載する事後保全に比べ、コストや手間がかかる方法ではありますが、故障リスクの低減が可能になるうえ、作業計画に支障を来すことなく実行出来るのがメリットです。また、故障した際に発生する修理代や、修理作業中に業務が停止するリスクを勘案すれば、長期的にコスト削減に繋がる保全方法だとも言えるでしょう。
事後保全
事後保全は、機器や設備が故障したときに行われます。故障した時点で初めて対応をするため、予防保全のように定期的な清掃・点検を行うコストや手間がかからないのが最大の特徴と言えるでしょう。また、業務に支障を来さない程度の軽微な故障であれば、事後保全の方が保全にかかるコストを抑えられるとも言えます。しかし、業務を停止せざるを得ないレベルの故障が発生した場合は、復旧までに時間がかかるケースも多く、その業務に関連する作業計画の見直しが必要になってきます。長期的にはコストや手間がかかる可能性が高い保全方法と言えるでしょう。
予知保全
予知保全は、データやセンサーなどを用いて劣化や故障の兆候を予測し、事前に対応することです。故障が起きる前に保全する点は予防保全と同じですが、予防保全が常に全ての機器や設備を保全するのに対し、予知保全は故障や劣化の兆候があるものにだけ対応します。予防保全のように、故障していなくても設定した期限を過ぎたら部品を交換するといったコストや手間がかからず、効率的かつコストを抑えた保全が可能です。また、データやセンサーを用いることから、少ない人数でも保全作業が可能になる点でも、予知保全は優れた保全方法だと言えます。
設備保全の目的と必要性について

ビルメンテナンス業の内の業務用エアコンにおいての設備保全を行う目的と必要性について、本項目では詳しくご説明させて頂きます。是非、目を通してくださいね。
目的は?
業務用エアコンの設備保全を行う目的は、業務用エアコンが異常を起こして停止したり、壊れたりするのを防ぐことです。また、故障しても停止している時間を最小限に抑えることや、新たな業務用エアコンに交換するまでの時間を出来るだけ長くすることも設備保全を行う目的の一つと言えます。
必要性は?
ビル内で多くの人が利用する機器や設備の快適性や安全性を維持し、長期間に渡って快適に過ごせる環境を保つために、業務用エアコンの設備保全は欠かせない業務です。ビル内設備のひとつである業務用エアコンが常に最大限の機能が発揮出来るよう、しっかりと保全を行わなければなりません。また、フロン排出抑制法により、フロン類を冷媒に使用している業務用エアコンについては、定期的な点検が義務付けられています。そちらについては、過去のコラムでもご紹介しているので、よろしければこちらも見てみてくださいね。
まとめ
今回は業務用エアコンにおける設備保全について、詳しくご説明させていただきました。設備保全とは機器や設備を不備や故障なく長期間に渡って維持するために行う計画的な点検を指しますが、実際は人材不足や多忙などによる影響からそのメンテナンス業務はどうしても事後対応になってしまいがちです。しかし故障してしまってからでは、もとの状態に戻すコストや時間が増大してしまい、管理者の負担が更に増えてしまいます。
管理者の負担を軽減し、更にビル内の快適な環境を維持するためには、設備保全の徹底が欠かせません。そこで近年では、AIやIoTといった技術を活用することで、突発的な空調機の故障を事前に防いだり、万が一の際の素早い対応を可能にするための実現を取り組んでいます。
より豊かに快適な生活を過ごしていくためにと、日々進化が伴っているメーカーの技術。これからもその進歩に、目が離せませんね。